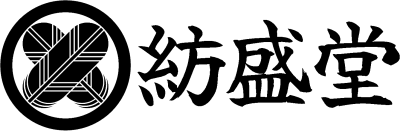刀装具の世界に足を踏み入れると、ほどなくして「正阿弥(しょうあみ)」という名前に出会うことになります。古美術店の棚に並ぶ鐔(つば)の極め札、刀装具の入門書のページ、あるいは祖父の遺品の桐箱の中。どこへ行っても「正阿弥何某」という名が目に飛び込んでくるのです。
江戸時代の中期から幕末にかけて、正阿弥を名乗る金工の数は他のどの流派をも圧倒していました。蝦夷地と琉球を除けば、日本全国のどこに行っても正阿弥の作品と出会えたと伝えられています。刀装具に関するどのような書籍にも、必ずといってよいほど正阿弥の作例が掲載されているのは、そのためです。
しかし、その「数の多さ」ゆえに、正阿弥はしばしば誤解されてきました。幕末に粗製濫造された低品位の作品が世に出回ったことで、「正阿弥=数は多いが質は低い」という印象が定着してしまったのです。
本稿では、そうした固定観念を一度脇に置き、室町時代の史料に記された正阿弥の本来の姿を辿ってみたいと思います。そこには、今日の評価とはまったく異なる、格式ある「銀師」の姿が浮かび上がってくるのです。
👇️前回の記事はこちら
もくじ
正阿弥とは何者か
正阿弥の発生は、室町時代初期の応永から永享の頃にまで遡ると考えられています。ちょうど足利六代将軍・義教の時代、いわゆる「北山文化」が最盛期を迎えていた頃のことです。
この時代、将軍家の周辺には「同朋衆(どうぼうしゅう)」と呼ばれる人々が存在していました。彼らは武士でも公家でもなく、将軍の側近くに仕えながら、茶の湯・連歌・芸能・工芸など、文化的な雑務全般を担う存在でした。使い走りや配膳から、唐物(中国渡来の美術品)の目利きや座敷飾りの演出まで、その職掌は広範にわたっていました。
正阿弥は、この同朋衆の中から生まれた金工集団であったと考えられています。そして彼らの本来の職能は「銀師(しろがねし)」、すなわち銀を中心とした金属細工師でした。
この「銀師」という呼称は重要です。後藤家が将軍家に仕える士分(武士の身分)を持ち、制度の中で格式を築いた「御用金工」であったのに対し、正阿弥は職能技術者としての同朋であり、武士ではありませんでした。しかし、だからこそ正阿弥は、上層から中層にかけての幅広い顧客層に対応できる柔軟な存在でもあったのです。
注文があれば太刀の金具も打刀の鐔も、金・銀・赤銅・鉄・真鍮を問わず、あらゆる素材を使いこなして制作しました。後藤家が主に金・銀・赤銅を用いて打刀や腰刀の三所物(目貫・小柄・笄)を専門としていたのとは対照的に、正阿弥の制作範囲は装剣金具全般に及び、さらにその外にまで広がっていたと考えられています。
室町幕府の御用達
正阿弥が単なる「数の多い金工集団」ではなく、室町幕府と深い関わりを持つ格式ある存在であったことは、当時の史料によって裏付けられています。
権大納言・山科言継(やましなときつぐ)が残した日記「言継卿記」は、大永七年(一五二七)から天正四年(一五七六)に至る約五十年間の記録です。戦国時代の公家の日常を細かに映し出したこの日記に、正阿弥が直接登場する場面があります。
元亀二年(一五七一)五月二十九日の条に、次のような記述があります。公卿の正親町邸で竹の子汁を振る舞う席が設けられ、山科言継自身のほか、竹内三位入道、大館治部少輔、そして「銀師の正阿弥」が列席したというのです。
この記述は、正阿弥が単なる職人ではなく、公家や幕府の重職と同席できる立場にあったことを示しています。列席者の中で正阿弥だけが身分の隔たりがあるとはいえ、その名が記録に残されたこと自体、当時の正阿弥の社会的な位置づけを物語っています。
さらに遡ると、天文九年(一五四〇)の「大館常興日記」にも正阿弥が登場します。
この記録には、「銀師の正阿弥右衛門三郎」が幕府との間で土地に関する揉め事を抱えており、大館氏がその仲介に当たったことが記されています。そして注目すべきは、「正阿弥は昔から幕府の御用を仰せつけられてきた者である」という一文です。
この記述は、正阿弥が室町幕府の御用達として長年にわたって機能していたことを明確に示しています。後藤家の乗真が壮年期にあったこの時代、正阿弥もまた幕府の重職と深い繋がりを持っていたのです。
今日の正阿弥に対する一般的な評価と、この時代の正阿弥の実際の立場との間には、大きな隔たりがあります。室町時代の正阿弥は、決して「数は多いが格の低い金工集団」ではなかったのです。
地透鐔の発生と正阿弥の役割
正阿弥の歴史を語るうえで欠かせないのが、「地透鐔(じすかしつば)」の発生との関わりです。
鉄地に文様を透かし彫りにした地透鐔は、打刀(うちがたな)の普及とともに生まれた、日本独自の刀装具の形式です。その発生時期については諸説ありましたが、江戸時代の刀装具研究家・榊原香山(さかきばらこうざん)が著した「本邦刀剣考」(安永八年刊)に重要な記述があります。
香山は古文書「室町家記」を引用しながら、「鐔に透かしを施すことは古来なく、足利義教将軍の物数寄(ものずき)によって始まった」と述べています。つまり地透鐔の発生は、六代将軍・義教が活躍した永享年間(一四二九〜一四四一)頃のことであり、正阿弥の発生時期とほぼ一致するのです。
この時代、打刀の制作が盛んになるとともに、正阿弥・京・金山・尾張などの地透鐔が創始されたと考えられています。新しい武器としての打刀に相応しい、新しい形式の鐔が求められた時代でした。
そして、足利義教の物数寄に応えて実際に地透鐔を制作したのは、同朋衆の中にいた正阿弥であったと考えられています。将軍家の周辺に仕え、新しい文化の担い手であった同朋衆の中から、新しい打刀の様式に相応しい鐔の形式が生まれたとすることは、歴史的な文脈からも自然なことでしょう。
現存する古い正阿弥の透鐔の中には、深く澄んだ紫色の地鉄に、上品で優美な肉彫り地透しが施されたものがあります。薄手で丸耳、磨地という作り込みは、六代将軍義教の好みに沿ったものと伝えられています。そうした作品を手にするとき、室町の北山文化の高雅な息吹が、数百年の時を超えて伝わってくるような気がします。
後藤家との対比
正阿弥を理解するうえで、後藤家との対比は欠かせません。しかし、この対比はしばしば「優劣」の問題として語られてきました。それは正確ではありません。
後藤家は、将軍家に仕える士分を持ち、一子相伝で作風を守り続けた「御用金工」です。その美学は、能楽・水墨画・文芸と同等の地平に立つ確立した様式美であり、室町時代の上層社会において最も尊重された芸術の流れの中にありました。後藤家が「頂点」として制度的な美を支えたのは、まさにその格式と様式の一貫性によるものでした。
一方の正阿弥は、武士ではなく職能技術者としての同朋でした。京都の正阿弥が全国を統括するような管理体制を持たなかったため、各地の金工が独立して「正阿弥」を名乗り、それぞれの地域の需要に応じて活動しました。統一的な様式を持たないことは、裏を返せば、あらゆる顧客の要望に柔軟に応えられる強みでもありました。
後藤家から派生して長く繁栄した流派は、横谷流と加賀後藤が目立つ程度です。これに対し、正阿弥から影響を受けて発展した流派は、埋忠・奈良流・肥後金工群・越前・水戸・長州・会津・秋田など、全国に広がっています。町彫りの大きな根幹を築いたのは、実は正阿弥であったといえるのです。
「後藤家が別格に位の高い特別な刀装金工であるとすれば、正阿弥こそが後藤家よりも歴史の古い一類であって、室町時代以来の刀装具の世界を牽引するもう一方の手であった」──一次資料の著者はそのように述べています。頂点と裾野、制度と多様性。この二つの流れが交わることで、日本の刀装具文化は豊かな広がりを見せてきたのです。
正阿弥の作風の特徴
正阿弥は統一的な様式を持たないとはいえ、作品に共通して見られる技術的な特徴はあります。鐔の切羽台(せっぱだい)・櫃穴(ひつあな)・耳(みみ)の作り込み方、そして金銀の布目象嵌(ぬのめぞうがん)の技法は、正阿弥の作品を見分けるうえで重要な手がかりとなります。
布目象嵌とは、金属の地に細かな格子状の切り込みを入れ、そこに金や銀の薄板を叩き込んで固定する技法です。この技法は正阿弥が得意とするもので、鐔や目貫の装飾に広く用いられました。後藤家が赤銅魚子地(あかがねなこじ)に高彫りで金銀色絵を施す技法を基本としたのとは対照的に、正阿弥は素材や技法の選択において幅広い自由を持っていました。
素材についても、正阿弥は金・銀・赤銅・素銅・鉄・真鍮など、あらゆる金属をこだわりなく使用しました。後藤家が江戸幕末まで鉄や真鍮をほとんど使用しなかったのとは大きな違いです。この素材の多様性は、正阿弥が幅広い顧客層に対応していたことの証でもあります。
意匠(デザイン)の面では、龍・虎・獅子といった威厳ある題材から、四季の草花・虫・鳥・吉祥文様など生活に身近なものまで、実に幅広い画題が取り上げられました。後藤家が能楽や中国の故事に基づく格調高い題材を中心としたのに対し、正阿弥は時代や地域の好みに応じて柔軟に意匠を変化させました。この適応力こそが、正阿弥が全国に広まった大きな理由の一つでもあります。
各地の正阿弥
正阿弥の最大の特徴は、その地理的な広がりにあります。京都を発祥の地としながら、正阿弥の名は全国各地へと伝播し、それぞれの土地で独自の展開を遂げました。
秋田・会津・長州・肥後・阿波・越前・水戸──これらはほんの一例に過ぎません。各地の正阿弥は、その土地の武家や町人の需要に応じながら、地域の気風や文化を反映した作品を生み出しました。京都の正阿弥が洗練された意匠を追求したのに対し、地方の正阿弥には素朴で直截的な表現が見られることも多く、そこに地域性の豊かさがあります。
長州(現在の山口県)の正阿弥は、京正阿弥・京埋忠との繋がりが強く、在銘の作品が比較的多く残されています。河治・岡本・岡田といった名を持つ長州鐔工の作品には、京正阿弥の技法を基礎としながら、独自の発展を遂げた様式が見られます。
肥後(現在の熊本県)では、細川家の庇護のもとで独自の金工文化が育まれました。肥後金工群と呼ばれる一群の金工たちは、正阿弥の技法を基礎としながら、武骨で力強い独自の様式を確立しました。
こうした各地の正阿弥の多様性を理解することは、日本の地域文化の豊かさを理解することにも繋がります。統一的な様式を持たなかったことは欠点ではなく、むしろ各地の文化と深く結びつく力の源泉だったのです。
古正阿弥の再評価
今日、正阿弥に対する評価が概して低いのは、江戸時代後期から幕末にかけて、各地で作位の上がらない品が大量に世に出たことが大きな原因です。その印象が正阿弥全体に投影され、「粗製濫造の金工集団」というレッテルが貼られてしまいました。
しかし、一つの流派の末期の低位の作品をもって、その流派全体を評価することは公平ではありません。室町時代から江戸時代初期にかけての「古正阿弥」の作品には、後藤家に匹敵するほどの技術と格調を備えたものが存在します。
室町時代末期の古正阿弥の作品の中には、最上の素材を用い、後藤家の技術に匹敵する出来栄えを示すものがあります。隙のない造形と真然とした風格は、その出自の正しさを物語っています。しかし今日では、こうした作品の多くが「古金工」や「古美濃」として括られ、本来の価値が十分に認識されていないのが現状です。
近年、透鐔の分野では古正阿弥の再評価が著しく進んでいます。正阿弥は本来が「銀師」であり、金工作品においても多くの優れた作品を残しているはずです。室町時代の史料が示す正阿弥の格式ある姿を念頭に置きながら、改めてその作品と向き合うことが、今求められているといえるでしょう。
刀装具史の半分を担った存在
「正阿弥を正しく理解すれば、わが国の装剣金工のおおよそ半ばを把握することになる」と言われます。この言葉は、単に数の多さを指しているのではありません。
室町時代の同朋衆の中から生まれ、銀師として幕府の御用を担い、地透鐔の発生に深く関わり、全国に広がる町彫りの根幹を築いた正阿弥。その歴史は、日本の刀装具文化の「もう一つの大きな流れ」そのものです。
後藤家が制度と格式によって刀装具の美を高みへと引き上げたとすれば、正阿弥は大衆的な広がりによって文化の基盤を支えました。この二つの流れを理解することなしに、日本の刀装具史を語ることはできないのです。
刀装具の世界に入ったばかりの方が最初に手にするのが正阿弥の作品であることは多いでしょう。しかしそれは、単に「数が多いから」ではありません。正阿弥は、室町の昔から日本の刀装具文化の裾野を支え続けてきた、歴史の深い存在なのです。その素顔を知ることは、刀装具という世界の奥行きを知ることに、そのままつながっています。
参考文献
本記事は、以下の書籍に基づいて構成しています。
『文化の中の刀装具』橋本晴夫 著、里文出版 出版、2006年(平成18年)10月 刊
一部の表現や解釈については筆者の視点を含むものであり、歴史的資料の解読・編集にあたっては慎重を期しています。
職人の流儀
正阿弥の鐔を手に取ると、いつも少し不思議な感覚がある。後藤家の作品のような、格式の重さとでもいうべき緊張感とは違う。もっと素直というか、こちらに向き合ってくるような感じがする。持ち主の好みに誠実に応えようとした職人の仕事、という印象だ。
今回この記事を書くにあたって改めて調べていくと、その感覚には根拠があるのだとわかった。
山科言継の日記に残された場面──公卿の邸で竹の子汁を囲む席に、正阿弥(銀師)が幕府の重臣と並んで座っている。これを読んだとき、なんとなく「仕事がらみの気さくな集まりだな」と思った。格式のある席ではあるのだろうけれど、同朋衆というのは使い走りも掃除も御酒の奉行も引き受ける、何でも屋のような存在だったらしい。身分の序列でいえば決して上位ではない。それでも公卿とも武家とも食卓を共にできた。
仕事柄かもしれないけれど、これはよくわかる感覚だと思う。どんな素晴らしい技術があっても、クライアントが何を求めているかを知らなければ意味がない。宴席に顔を出し、贈答品を届け、場の空気を読む。そういう地道な接点の積み重ねが、結果として正阿弥の「何でも作れる」という幅広い作域を育てていったのではないか、と想像してしまう。
後藤家が「自分たちの様式そのもの」を求められていく道を歩んだとすれば、正阿弥は逆に「依頼者の美意識を忠実に形にする」ことに徹していた、とも言えるかもしれない。どちらが上ということではなく、これは全く別の職人の流儀だと思う。
その違いが、作品の多様性として今日まで伝わっている。
ところで、江戸時代の文学のなかに、正阿弥の行商人が登場する場面がある。
人差指が参百石が物、売に替姿の事
──井原西鶴「武道伝来記」巻三(元禄二年・一六八九年刊)
この章は、正阿弥の職人が刀の小道具(目貫・小柄・笄)を携えて武家屋敷を訪ね歩く場面として知られており、当時の武士が路上や屋敷の門口で刀装具を買っていたというリアルな日常が描かれている。「人差し指が三百石の侍の品物」を売り歩く──という題名からして、実用品としての刀装具がいかに武士階級に密着していたかが伝わってくる。
室町時代の幕府御用を務めた正阿弥が、元禄の世には庶民の日常に溶け込んだ行商の姿で文学にも登場する。その振り幅の大きさが、正阿弥という存在の本来の底力だったのかもしれない。
格式の鎧をまとわず、時代ごとの暮らしに寄り添いながら、しかし技術の水準を落とさなかった。そういう職人の仕事の形が、今の私にはとても魅力的に映っている。

紡盛堂のこと、もっと知っていただけたら嬉しいです。
刀装具や日本刀、日本文化にまつわる日々の気づきを、SNSでも発信しています。
よろしければ、こちらもあわせてご覧ください。
このブログが、ほんの少しでもあなたの感性に響くものであれば幸いです。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。